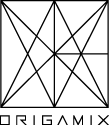STORY藍で和紙布を染める
和紙から生まれた布の機能性を最大限に生かした製品を世に送り出す、細川機業のファクトリーブランド「ORIGAMIX」。
その第1弾として誕生した「和紙布スリッポン」は今年で6年目を迎え、この夏には藍染めによって染め上げた限定商品が登場する。
和紙を織ることで生み出される素材を、日本古来の染色技術で染めたのは、同社の隣町に当たる富山県魚津市で蓼藍を育て、
染色を行う職人。植物由来の和紙布に天然の染料で染め上げるという、新たな挑戦だ。

富山県北東部に位置し、富山湾と北アルプスに挟まれた魚津市。海と山がせめぎ合う独特の地形から、人々の営みは山から湧き出る伏流水の流れに沿って形作られてきた。鹿熊という集落もそのひとつ。「その昔は金山によって栄えた城下町だった」と地元の老人たちは語り継いでいる。

現在は50世帯ほどの人々が肩を寄せ合う静かな山村で「藍染め屋aiya」として活動する南部歩美さん。いくつかの幸運な出会いを経て2018年に鹿熊に移り住むと、手に入れた古民家の台所を染め場に変え、畑を借りて染め液の原料となる蓼藍を栽培し、藍染めと向き合う日々を送るようになった。

そもそも「藍染め」とは何だろう?
南部さんに藍染めのイロハを教わることに。蓼藍という植物に含まれる色素を用いた藍染めは、奈良時代に朝鮮半島から日本に伝わったとされている。藍は解毒や抗炎症作用のある薬草として重宝され、蓼藍で染めた生地には殺菌効果や防虫効果があったことから、上流階級、武士、そして江戸時代には庶民のあいだで愛用されたという。藍染めは世界各地で培われてきた染色技術だが、原料となる植物は土地によって異なる。共通しているのは「インディゴ」と呼ばれる青い色素を利用する点。東アジアでは蓼藍の葉に多く含まれることから利用されてきた。蓼藍を収穫するのは真夏。刈り取った葉を天日干しにして乾燥させた後、山のように積み上げる。

そこに水をかけて筵(藁で編んだ敷物)をかけ、切り返しの作業を繰り返すことで発酵が進む。約2ヶ月かけて堆肥化させると「すくも」と呼ばれる染料のもとができる。
出来上がったすくもは1年近く寝かせてから、染め液を仕込むために使用する。その際に使用するのは灰汁や日本酒などの天然素材だけ。南部さんは地元の果実農家から出る薪の灰をもらってきて自ら灰汁を作り、すくもと混ぜ合わせて10日程度かけて染め液を完成させる。こうした一連の流れを「藍を建てる」と表現する。南部さんは昨年秋に初めて、自ら栽培した蓼藍の葉で仕込んだすくもを使って藍を建てた。同じ土地の空気と水で育ったからなのか、発酵はとてもスムーズに進み、常に安定した色の出る染め液が出来上がった。
機械漉きの和紙は、障子紙や書道紙、断熱材などにも活用されています。

ORIGAMIXの和紙布は、この「メイドイン鹿熊」の藍で染め上げている。大きな甕には染め液がたっぷりと入っていて、わずかながら発酵臭が漂っている。甕の底にはヘドロ状になったすくもが溜まっているそうだ。南部さんは「天然灰汁醗酵建て」という、江戸時代から続く伝統技法で藍を建てる。天然由来の素材のみを用いた、環境にも人間にも優しい染色法だ。彼女は素手で染色するために手はいつも青く染まっているが、肌荒れ等は一切ないという。生地を染め液に浸し、両手で丁寧に色を染み込ませる。布を広げ空気に晒し、再び甕の中で染め重ねる。それを何度も繰り返し、表現したい色に染まったら一晩水にさらしてから天日干しする。

「藍はグラデーションに富んだ染色で、薄い色から濃い色まで染め分けることができる。染める回数、染め液の状態で出る色が違う。そこが藍染めの面白さ」と南部さんは言う。100%オーガニックな染め液であるがゆえに、水温やPH値など様々な要因によって染まり具合は毎回変化する。中でも色を左右するのは「染め液の状態」という。

「働きすぎればダウンするし、休みすぎても怠け癖がつく。人間とそっくり」と南部さんが例えるように、染め液は生き物のように日々変化する。一度に大量の染色をしてしまうと色が出にくくなり、天候や温度にも敏感に反応する。建てたばかりの元気な染め液であっても、雑菌が湧けばあっという間に腐敗するし、3日も放置すれば死んでしまう。なので毎日状態を確認して、調子を整える。貝灰を加えたり、小麦粉由来のふすまを鍋で炊いて与えて、染め液を常に良い状態に保つ。彼女は染め液に「藍ちゃん」と名付け、我が子を育てるように接している。

蓼藍を育てている畑を案内してもらった。一反あるかないくらいという広さの畑では、まだ背の低い苗が若葉をたくさん出し、元気に育っていた。蓼藍栽培が盛んな徳島県では日当たりがよく水はけの良い土地に藍畑が広がる。四国に比べて冷涼な北陸地方は、蓼藍にとって最適の環境とは言えないかもしれない。けれど強靭な植物であるがゆえ、日当たりの悪い山間部というハンディキャップに負けることなく、逞しく生育している。「蓼食う虫も好き好き」ということわざもあるように、粘り気があり苦い蓼藍の葉を食べる野生動物もいない。そうした観点から蓼藍の栽培は山間部の新たな産業になる可能性を秘めているという見方もできる。将来的に作付面積を増やして、染め液の生産量も増やしていきたいと南部さんは考えている。

とはいえ畑仕事と染色を両立させるには、自分ひとりの力では不可能だ。畑を起こし、畝を立て、種から育てた苗を畑に定植する。地域の人々の協力無しには成り立たない。しかし南部さんが暮らす鹿熊は住民の高齢化や過疎化といった現実に直面している。「藍染めを通して地域を元気にできないか?」と考えていた折、コロナ禍によって人とのつながりの大切さを改めて感じた彼女は「Tsunagu Project」を立ち上げた。ヒト・モノ・コトを繋ぎ新しい可能性を生み出したい、との思いからだ。南部さんのもとには、地域づくりや農業体験に興味を持つ若い世代が、すでにSNSを通じて集まっているそうだ。染め物を軸とした持続化可能な里山コミュニティが、やがて富山に誕生するかもしれない。

PRODUCTSプロダクツ
限定カラー「天然藍染め」
オリガミクスの和紙布工場がある上市町のおとなり、 魚津市鹿熊で育った蓼藍を使って手染めされた天然藍染めモデル。